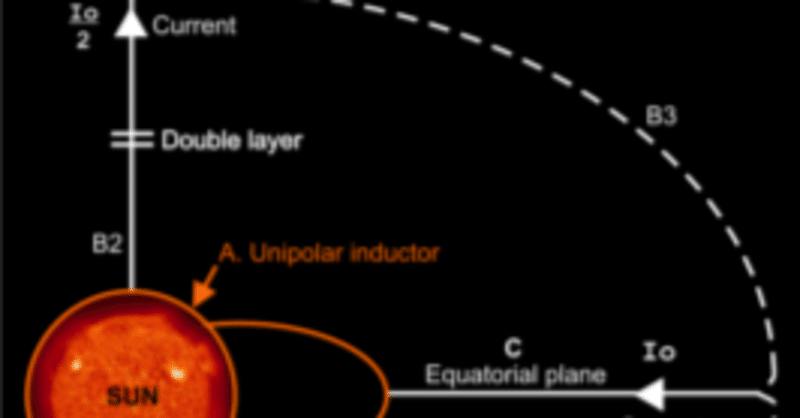Category: Classic Science
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 >>
2025/10/13
反陽子の寿命が少しだけ伸びる
反陽子を液体ヘリウムの中に入れると、その3%ほどの寿命が延びるそうだ。
https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-03402011/034020111991jisseki/
伸びると言っても3usになる程度なのだが、その原因が不明とのこと。
電気的地球科学では陽子が崩壊しないのはニュートリノの入射により、電荷が供給されているからだと予想している。電荷が反対で大きさが同じ反陽子なら、陽子と同じようにニュートリノが入射して電荷が供給されるので、崩壊しないと思っていたがそうではない。
陽子の膜が一部はがれ、内と外が逆転したものが電子と考えている。中間子は電子が大きくなった状態で、それが短時間のうちに大きさを変えて、電子まで縮小する。
π -> μ -> e
縮小するごとにニュートリノを発生させる。徐々に小さくなるのではなく、段階的に急激に縮小するようだ。急激に縮小した際の電界のパルスがニュートリノだ。陽子は崩壊するならK+中間子を経てe+になるらしいことが予想されている。
では反陽子はk-中間子を経てeに崩壊するのだろうか?色々調べたがまだわからない。
対称性が保たれているなら、反陽子は陽子と同じ寿命のはずだ。しかし、反陽子はあっという間に消滅する。これも対消滅とはわかっていない。
電気的地球科学では陽子は内部が空洞で、表面を膜のようなものが囲んでいると考える。膜の裏側はマイナスの電荷だ。対称性がないならこの膜は表と裏で性質が違うことになる。
2025/06/21
反重力装置の試作をクラウドファンディングで準備中
いつまでも理屈ばかり書いていても仕方ないので、反重力装置を試作するための費用をCAMPFIREでクラウドファンディングすることにしました。いま準備中ですが、公開する予定のページを見ることができます。応援、よろしくお願いします。
2025/05/27
原子核へのアプローチ
電気的地球科学ではその基本となる原子構造をSEAM(static electron atom model)のように原子核は複数の陽子が中間子(電子)により結合されていると予想している。しかし、標準理論ではどのようなアプローチをとっているのか?一度考えてみても損はない。
原子核の構造は量子力学が登場した1930年代から言及されていた。最初に原子核の模型が登場したのは液滴模型だ。原子核は陽子と中性子が強い力で結合しており、液体のように変形すると考えられた。たとえば、ウランの核分裂は液状の原子核に中性子が当たると中央にくびれが入り二つに分離する。分離した核断片は互いの電気的反発力で飛び去って行く。液滴模型は核分裂を説明するのに都合がよかった。

https://ne.phys.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld3/3Part2/3P27/summary_3P2.htm
原子核にも原子のような規則正しい構造を求めたのが殻模型だ。殻模型では原子核内部は陽子と中性子が整然と並んでいる。殻模型は原子核の構造を計算することで、実験結果と比較できる。結果がわかりやすい予想と言える。殻模型をさらに微細に突き詰めたのがアルファクラスターだ。もっとも単純な水素原子核から重水素原子核、トリチウム、ヘリウムといった原子核が融合して出来ていく過程を説明することが出来る。SEAMはアルファクラスターを一歩進めた模型ということもできる。

標準モデルでは原子核内部にマイナスの電荷が存在することを認めていない。しかも、液滴模型、殻模型、アルファクラスターのいずれも原子核内部では陽子と中性子が区別がつかないことを述べている。また、原子核のハサミ振動といった変形について、具体的な仕組みを提案できないでいる。陽子同士が励起した電子で結合され、電子の一部は陽子に食い込んでいるとするSEAMは、原子核の具体的構造を予想できるうえ、陽子に食い込んだ電子の電荷が外に出ないことで、質量欠損も説明できる。

原子核が変形することも、1個あるいは2個の中間子で結合されている個所が動くことで理解できる。

殻模型、アルファクラスターからSEAMへ至るには、中性子の複合構造、原子核内部の電子の存在などハードルが高いが、理論としては優位性があると思われる。
2025/01/31
陽子表面で起きていること
SEAMでは陽子振動がガンマ線の定在波を作り、軌道電子の量子跳躍を生んでいると予想している。原子核の近くに強力なガンマ線をあてると対生成が起こり、電子と陽電子が生まれる。これらのことから陽子は柔らかな球体で複雑な振動をしていると考えられる。
その様子を示した動画があった。ISSの微小重力下で水玉に音波を当てる実験だ。周波数を変えていくと水玉の表面が複雑な動きをして、ついには小さな水玉が飛び散っていく。まるでガンマ線を当てたときの対生成のようだ。
2024/03/27
量子もつれとパウリの排他律
量子力学の最初に出てくるのが、プランクの量子、光量子仮説、ボーアの原子模型、波動関数、量子跳躍、パウリの排他律、不確定性原理、シュレディンガー方程式といった一連の概念だ。一つでも欠けると量子力学は成り立たない。でも、これらが生まれたのは、いずれも中性子が発見される以前であることにほとんどの人は気が付いていないのではないか?ニュートリノが発見されるのは、このずっとあとになる。そして不思議なのは、そうした意味が後付けのように付け加えられることだ。
不確定性原理がその代表例で、シュレディンガー方程式が主張された後、確率波が収束するのはいつなんだ?という疑問を解決するために考えられた。シュレディンガー自身は自分が主張している方程式が現実の現象とどのようにリンクしているかは考えなかったようだ。それもそのはずで、シュレディンガーは統計力学を1個の粒子に当てはめただけだったからだ。ネコを持ち出して、その矛盾を指摘したり、晩年は「量子力学は統計力学から生まれ、統計力学に帰る」と言った。
ドブロイの波動関数はアインシュタインの光量子仮説という曲がりなりにも根拠があった。波と考えられている光が粒子の性質を持つなら、粒子とされている電子が波の性質を持ってもいいではないか?論文を読んだアインシュタインが納得したらしい。
しかし、パウリの排他律と量子跳躍ではこの仕組みを説明できなかった。現在でも、シュレディンガー方程式から導出できると主張されるが、そのはっきりとした仕組みは説明されていない。
量子跳躍の根拠はバルマーが発見した輝線スペクトルだ。希薄な水素などのガスをガラス管に入れ、高電圧をかけると発光するが、そのときのスペクトルが飛び飛びの波長をとる。この原因は軌道電子の取る軌道半径が飛び飛びであるからだと主張された。ボーアの原子模型とラザフォードの原子模型の大きな違いだ。なぜ飛び飛びの半径を持つか標準理論では現在でもわかっていない。SEAMでは原子核にニュートリノが入射する際に放射されるガンマ線の定在波が原因だと主張している。
パウリの排他律は同一軌道上に同じスピンをもつ電子は入れない、というルールだが、これも理由が定かではない。電子のスピンは最初電子が自転していると想定されたが、途中から自転という物理現象ではなく、数学上の概念に変わった。なぜ自転から概念に変わったのかと言えば、磁場が発生する状態では電子の自転速度が光速を超えてしまうからだ。また、電子の大きさが確定できなくなったこともある。古典物理では電子の半径は明らかだったが、量子力学では不定になってしまった。これも電子が確率分布として捉えられるようになった結果だ。
なぜ同一軌道に同じスピンをもつ電子が入れないのか? SEAMなら答えは簡単だ。まず、原子核のプラスとマイナスにゆるくつながれた電子が、ガンマ線の定在波の谷間に落ち込んでいる。このゆるい束縛された状態で電子は周囲からの電磁波の影響で小さな半径で回転する。これがスピンだ。電子は周囲の電子に対して、反発するので、一番近い電子とは反対側に回転する。たとえば、もっとも内側の軌道では原子核を挟んで2個の電子が小さな半径でスピンするが、このとき互いに電気的反発力を及ぼし合うので、スピンは異なる向きになる。幾何学的には非常に複雑な軌道を描くことになるだろう。複数の要因から軌道電子はカオスの状態にあると考えられる。予想するのは難しいが、けっして霧や雲のような状態ではない。

電子軌道は原子量が増えるほど複雑になる。原子核の構造も球ではなく、凸凹になっていくからだ。
量子もつれはその根拠となったパウリの排他律を無視するように、まるで魔法のルールとして考えられている。量子もつれという言葉をネットで見るたびに量子力学の迷宮の深さを感じざるを得ない。