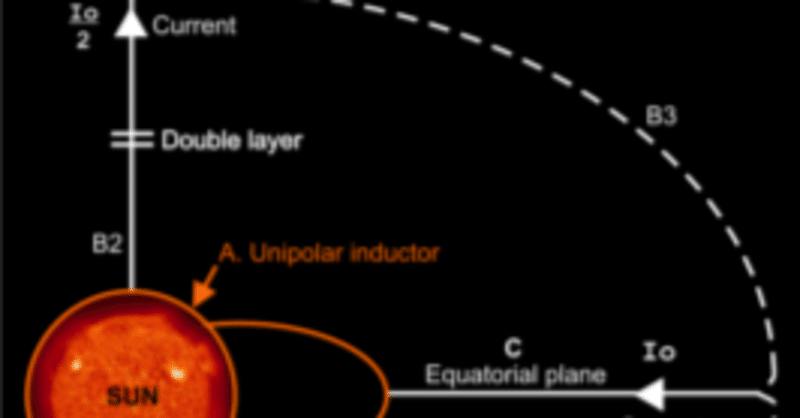Archives for: 2018年October
2018/10/24
超新星爆発ー電気的地球科学による解釈
ニュートリノが大量に放出される現象として、超新星爆発がある。超新星爆発は核融合による圧力が重力を上回ることで起きるとされる。しかし、電気的宇宙論では恒星はZ-pinchによる磁場の収縮で星間物質が濃縮された状態だ。恒星内部にはプラズマによる電気的反発力が働くが、この反発力が解放されても超新星爆発のようにニュートリノを放出するメカニズムはない。恒星が放出するニュートリノは、電子ニュートリノで、陽子と電子の衝突、離散によるからだ。
2つの可能性が考えられる。超新星爆発と大量のニュートリノは関係ない。カミオカンデでニュートリノを観測した時刻に新たな超新星が見つかったことが、超新星とニュートリノを結び付けている。カミオカンデには、正確なニュートリノの飛来方向を測定する能力はない。同時刻という関係だけだ。
もうひとつは電気的宇宙論が予測する恒星のメカニズムに未知の現象があることだ。ニュートリノは陽子、電子に電荷を運ぶ役割を持つと考えている。ニュートリノの密度が減少すると、原子は結びつきが弱くなり、崩壊する、これが電気的地球科学による予想だ。逆にニュートリノが増えたらどうなるだろう?
電子より陽子は大きいためニュートリノが多く通過する。大量のニュートリノが陽子に過剰な電荷を与えると、陽子同士が大きな反発力を持ち、恒星表面のプラズマが飛散するのではないか?
なんらかの拍子にニュートリノが増加したとする。大量のニュートリノを受けた陽子が急激に反発して動く。動いた陽子が陽子、あるいは電子と衝突、ニュートリノが再び大量に発生する。
核爆発では、中性子の幾何級数的増加が即発臨界、核分裂の急激な発生を起こす。これと同じようなメカニズムで、ニュートリノの急激な増加が陽子の反発力を増大させ、爆発的なプラズマの離散を招く。
何がニュートリノを増加させるきっかけになるのか? 流入する星間物質の電圧が増えるためだろうか? もう少し考える必要がある。
2018/10/21
距離、オレは何を考えているのか?
このブログには、ドラフト機能があって、発行する前に書き溜めておくことができる。発行に至らないテキストも多い。途中まで書いておいて、結論が出なかったり、あまり気が乗らないときもドラフト状態にしておくことが多い。
普段何を考えているかといえば、たいしたことは考えていない。ハンダ付けしていたり、ネットを闇雲にみていたり、ラジオを聴いていたりするだけだ。たまに気になる内容を見つけると、じーっと考えてみたりもする。たいていは結論が出ないことが多い。
いま気になっているのは、距離だ。空間という概念が数学上の概念であることを以前指摘した。縦横奥行は、幾何学から由来した考え方で、自然には本来空間は存在しない。とは、言ってみたものの手を動かせば、モノと手との間に距離がある。何かを持とうとすれば、その距離の違いで手が届く時間が違う。
電磁波の伝播でも、粒子と粒子の間は遠隔作用で一瞬で届くと考えた。一瞬とは距離がないことに等しい。質量は、モノに本来備わっている性質ではなく、加えられた力に対して起きる磁場の抵抗であることがわかった。時間は、生物の記憶がもたらす変化に対する感覚だ。自然には時間はなく、この一瞬しか存在しない。
では距離とは何だろう? モノとモノを区別できるのは、距離があるからだ。別々のモノは、同じ場所に存在できない。現在の人間の技術では、陽子、電子といった素粒子の違いを区別することは不可能だ。この電子は、1年前に見た電子と同じものだ! とは絶対に見分けることができない。それどころか、大量に存在する陽子には、個性がない。見かけはすべて同じだ。区別できるのは、位置の違い、つまり距離だ。
距離と空間とは違うのだろうか? おそらく幾何学で考えた瞬間にこの論考は無効になるだろう。距離はもっと根源的な意味を持つ。まー、とりあえず結論が出ないまま、この状態を記憶しておくことにしたい。
2018/10/14
物理学に潜む4つの間違い
いままで何度か現代物理学には間違いがあると書いてきた。ここでもう一度まとめてみた。
- 万有引力→ない。宇宙空間と地表の重力はちがうメカニズム
- 質量は重力を生まない。キャベンディッシュの実験は間違い
- 電気力線は中和しない。マックスウェルはファラデーの電気力線を勘違いした
- 空間は実在しない。アインシュタインは数学上の概念「空間」を検証せずに導入した
・万有引力→ない。宇宙空間と地表の重力はちがうメカニズム
17世紀の天文家の間では、引力と同じように斥力があると考えられて
いた。斥力を数式に入れると3体問題になるので解けなくなる。斥力
は無視された。
宇宙→電気引力・斥力 地表→EMドライブ
彗星の軌道計算では、非重力成分が考慮されている
スイングバイ、パイオニアアノマリー
相対性理論に引き継がれ、さらに「空間」という概念を実在として扱
ってしまう。
・質量は重力を生まない。キャベンディッシュの実験は間違い
鉛は反磁性体。地磁気で磁化され、反応する。Gは自転速度に相関し
ている。地球磁場は自転により生じる。
地球の密度を5.4と推定。地球内部に比重の重いコアがあると推測し
た。重力のため地球内部が高温になっていて、マントルを対流させ、
プレートを動かしている。現代の地球科学に引き継がれた。
恒星はガスが重力で集まって、内部の圧力が高くなり、核融合を起こ
していると考えるようになった。ブラックホールの根拠になってい
る。
鉛は反磁性体、地球磁場に影響される。
・電気力線は中和しない。マックスウェルはファラデーの電気力線を
勘違いした
クーロン力は、+、-が別々に真っ直ぐ対称に到達して、内部でベク
トルが合わさる。
ボーアの原子模型において、原子核(+)に対し電子(-)が周囲を
高速で回らなければならなくなった。量子力学の誕生を促し、不毛な
不確定性原理などを生んだ。
原子核にある中性子に電子が含まれる。
量子力学の成立はボーアの原子模型において、電子が原子核に落ちてしまうという問題がきっかけになった。電子が軌道を回転すると古典物理では、電磁波を放射して原子核に落ちてしまうからだ。でも、これはマクスウェルの電気力線の解釈での話し。
マクスウェルはファラデーの実験ノートを数式にまとめるとき、熱力学を考えていた。熱は伝達する途中で、熱い物質とつめたい物質が中和する。電気力線も同じように処理されて、プラスとマイナスが中和するとされた。数式にすると中和するとしたほうが簡単になる。
しかしファラデーはそのように考えていなかった。ファラデーの電気力線はプラス、マイナスが独立して対象に作用するものだった。プラスとマイナスは物質内部でベクトルが合算されて、作用する。この解釈では3体問題になるので、数式化できない。40歳年下のマックスウェルにファラデーは「これ、違うんじゃない」と言ったらしい。でも、食事を共にするくらいマクスウェルをかわいがっていたファラデーはそれ以上追及しなかった。(注:ファラデーはマクスウエルに自分の考えと違うと反対した、のが正しいらしい)
軌道上の電子を反発する力は、原子核の中にある中性子が持っている。中性子は陽子+電子だからだ。静的原子模型が量子力学を乗り越える理論に成るはず。
水素は、3個の陽子がくっつくプロトン化水素が多い。
陽子に直接電子がくっついたものが中性子
・空間は実在しない。アインシュタインは数学上の概念「空間」を検証せずに導入した
時空で重力を説明するためミンコフスキーの空間概念を取り入れた。
インフレーションでは真空が物質を生んでしまう。電磁波の伝播は空間が磁場と電場を交互に生み出しながら進む。
空間は魔法の存在。
4番目の相対性理論に関する部分は、万有引力の間違いに、さらに間違いを重ねてしまった。現代物理学をわかりにくくしている原因にもなっている。アインシュタインは19世紀に流行していた、数学理論を現実視するピグマリオン症の典型ともいえる。
ミュー粒子の寿命
ミューオンは、発生方法で2種類ある。ひとつは、宇宙線が大気に飛び込んで作られるミューオンで、もうひとつは実験で陽子線を使ってパイ中間子から人工的に作られるミューオンだ。ミューオンの平均寿命は2.2×10-6秒とされているが、これは実験で作られた場合の平均寿命だ。大気で作られるミューオンの平均寿命は推測でしかない。
ミューオンの平均寿命が長くなっているという考察は、宇宙線で作られたミューオンが予想よりも長い距離を飛んでいることが観測されたからだ。地上から6km上空で作られるミューオンが2.2×10-6秒では、700mしか飛ばないから地表では観測できないはずだからだ。その説明のため、光速に近い速度で飛ぶと相対性理論の解釈では時間が遅くなるので、長い距離を飛ぶことが出来る、と予想されている。その詳しい考察が次のPDFに書かれている。
http://rokamoto.sakura.ne.jp/education/physicsIIB/life1.pdf
でも、宇宙線から作られたミューオンの平均寿命は誰も測定したことがない。6km上空で作られたと予想して地上で観測できたという事実だけだ。特殊相対性理論では時間が遅れるとされるが、光速で移動する場合の時間の遅れを誰も実際に測定したことはない。
では何が起きているのか? 可能性として考えられるのは、大気から宇宙線で作られるミューオンが、光速より速い速度で移動していることだ。電気的地球科学では宇宙線の速度は光速より速い。ミューオンは超光速の宇宙線の衝突で飛び出たパイ中間子から生じる。ミューオンの速度も光の速度を超えていると予想できる。
では、GPSなどで宇宙空間で衛星に積んだ原子時計が時間の遅れを示している、という現象があるが、あれはどうなっているのだろう? 原子の励起周波数、あるいは半減期が変化している可能性がある。
ミューオンは非常に透過力の強い粒子だ。大気中で光の速度より速くても、ある程度の距離は進むことが出来るのだと考えられる。
2018/10/13
なぜ山では雨が多い?
湿った空気が山にぶつかると、高度が上昇して水蒸気が結露して雨になる、と普通は説明されている。日本では日本海で発生した大量の水を含んだ空気が偏西風に流されて、日本列島の山脈にぶつかり、雨、雪を降らせる。
山ではじっさいに雲が出来る光景を見ることができる。これを見てほしい。
雲は木の上から湧いてくるように見える。

ところで、植物が光合成を行うカルビン回路がある。カルビン回路は二酸化炭素と水から炭酸同化作用で炭化水素化合物をつくる。ATP合成ではあまった水素原子を放出する。カルビン回路は1秒間に17回サイクルを繰り返すといわれている。

カルビン回路中の葉緑素は、光を受けると電子を放出する。通常のこの電子は、ATPの合成に使われるとされている。植物は、太陽光があるときは、酸素、水素イオンと電子を作っているわけだ。これは雨の材料だ。
12H2O -> 6O2 + 24H+ + 24e-
しかし、もう少し観察すると、同じ植物のある平地では、雲の発生を見ることはない。水田などは格好の水蒸気の発生する場所と思えるが、水田から雲が湧いている光景は見たことがない。平地の林があれば、比較できるはずだが、残念ながら日本には平地林がほとんど残っていないのだ。
そこで予想できるのは次のようなメカニズムだ。
太陽光に含まれる紫外線が酸素をオゾンに変える。地殻内部から電子が放出されるが、電離層のプラスに引かれるので、電離層により近い山から大量の電子が出てくる。電離層からプロトンが降りてくる。電離層から降りてくるプロトンは、通常大気電流として観測される。大気電流が増えると地表と電離層の間で電位差が低下するので、気圧も低くなる。
低気圧が発生するのは、大気電流が増えることで、それはプロトンの移動が増えるためだ。大気中のプロトン濃度、通常は水素濃度として観測されるが、水素原子が増えるとオゾンと反応しやすくなり、雲が発生する。オゾンと水素原子の反応には地表から放出される電子が関わっている。
地表の電子がなぜ放出されるかという問題もある。これは、地殻内部に大量の電子があるためで、電子の持つ電位がばらばらであるため、誘電体バリア放電が起きていると考えられる。誘電体バリア放電については別にまた書きたい。